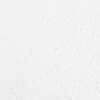「ちくわぶ」というおでんの具材はご存知ですか?ちくわぶは関西のおでんには入っておらず、関東のおでんに入っているという特徴があります。
おでんの具材や味付けには各地方で特徴があり、それぞれの地域で美味しいおでんが食べられています。
そこで今回は、関東や関西、北海道、四国、沖縄など、各地域ごとのおでんの特徴についてお伝えします!
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
No Image
おばあちゃんやご年配の女性の名前を見ると、カタカナだけの名前が多いと思いませんか?なぜ昔の女性の...
-

生地を水通しする方法!水通しが必要な素材と水通しが必要な理由
生地を水通しする方法について知りたいという人もいますよね!手芸などに使う生地は、素材によっては水通し...
スポンサーリンク
ちくわぶは関西のおでんにない?関東と関西のおでんの具材
おでんって、地域によって具材がちがいますよね?
あなたのおでんの定番の具材ってなんですか?
一般的におでんといえば、『大根・こんにゃく・ちくわぶ』と思いますが、これは地域によって、全く違うようです。
関東のおでんには『練り物』が多く、私がおでんの具材の定番だと思っているちくわぶも関東特有の具材なんだそうです。
ちくわぶの原材料は小麦粉。
小麦粉で作られているちくわのような形状の、もちもちとした食感がする食べ物です。
このちくわぶ、関西ではメジャーではないようです。ビックリ!関東のおでんの具材に見られる特徴としてあげられるのは、動物性タンパク質ですよね。
牛すじはもちろんのことタコ足やクジラの皮なんて言うものもあります。
関西のおでんにちくわぶがなくても変じゃない!おでんは地域によって違う
関東のおでんと、関西のおでん。
具材が違えば、出汁も全く違います!
昆布と鰹節というベースは同じですが、関東はそのベースに濃口醤油とみりん砂糖さけなどで味付けをし、具材をグツグツと煮込んで仕上げます。
それに対して、薄口醤油と塩で整えた透明な出汁であっさりと煮込むのが関西のおでんです。
最近ではご当地ラーメンならぬご当地おでんも注目を集めています。
その中でもひときわ注目を集めているのが『静岡おでん』
牛すじでとった真っ黒な出汁に黒はんぺん。
具材はすべて串に刺されていて、青のりや鰹節などを付けながら食べるのがポピュラーです。
静岡では、駄菓子屋さんの片隅におでんの鍋があり、子どもたちのおやつとして食べる習慣があったのだとか。
おでんから、地域性がわかるものなんですね。
おでんのちくわぶがないのは関西の特徴!北海道~関東のおでん
北海道のおでんは、昆布だしがベース。
しょう油と塩で味を整えて、具材に出汁を染み込ませます。
昆布をひいておでんを炊くこともありますし、じゃがいも(メイクイーン)が具材なのも北海道らしいですよね。
もちろん、ホタテやツブなどの貝類や、山菜なども具材になります。
東北地方のおでんは山菜や魚介類が豊富に入っています。
生姜味噌を付けながら食べるのが特徴。
焼き干しと昆布の透明な出汁で炊くのが東北地方のおでんです。
関東地方のおでんの具材はやっぱり『ちくわぶ』
このモチモチとしたちくわぶがおでんの出汁を吸って炊き込まれています。
魚を身だけではなく骨や軟骨などまるごと使って練られた『スジ』と呼ばれる練り物も関東のおでんでは欠かせない一品です。
関東の『スジ』と関西の『スジ』は全く別物ですから、注意するようにしましょう。
中部・中国・四国・九州・沖縄のおでんの特徴
名古屋のおでんはやっぱり『味噌』。
味噌で煮込んだおでんが親しまれています。
中国や四国地方では、愛媛風おでんといって、つけダレに付けながら食べるおでんがあります。
『みがらしみそ』という、麦味噌をベースにしたからし味噌を付けながら食べます。
愛媛風おでんは生姜醤油を付けながら食べるのが特徴。
九州や沖縄地方も独特なおでんがあります。
沖縄のおでんの具材はもちろんテビチ!
大きめの大根や卵などに、青菜などの葉物野菜を入れてさっと火を通して仕上げます。
ウインナーや島こんにゃくももちろん入っていますよ。
実は、沖縄っておでん屋台が多くあるんですよ。
暑い気候の土地柄ですが、おでんが根付いているんですね。
九州の博多風おでんは鶏からとった出汁に『餃子巻き』が具材なのが特徴。
長崎風おでんは、焼あごから出汁を取ります。
関西風のおでんが食べたい人におすすめのレシピ
関西では、おでんのことを「関東煮」言うことがあります。
かつおだしの江戸の煮込みおでんが関西に伝わり、新たに昆布だしが加えられて深みを増したものが「関東煮」となりました。
その、関東煮が関東大震災後に東京に逆戻りして普及したという歴史があります。
大阪の関東煮に欠かせなかった具材がとして上げられるのはクジラの「コロ」です。
クジラの「コロ」とはクジラの皮のこと。
クジラが貴重品になったため、クジラの「さえずり」(クジラの舌)とともに今ではなかなかお目にかかれない貴重なおでんの具材となってしまいました。
牛すじやタコ足など、動物性のものを煮込むのが関西風おでんの特徴の一つです。
京都地方では、湯葉もおでんの具材の一つです。
京都らしいですよね。
関西風のおでんを食べたいのなら、具材は大根・たまご・牛すじ・黒こんにゃく・タコ足・ロールキャベツ・結び昆布などをチョイスすると良いのでは?
おでんの汁を濁らせないコツは『グツグツ煮込まないこと』
お鍋の中をグツグツ煮込むと出しが濁ってしまいます。
あくまでも出汁を揺らさないように、弱い火で炊くのがおでんの極意です。
是非、試してみてくださいね。