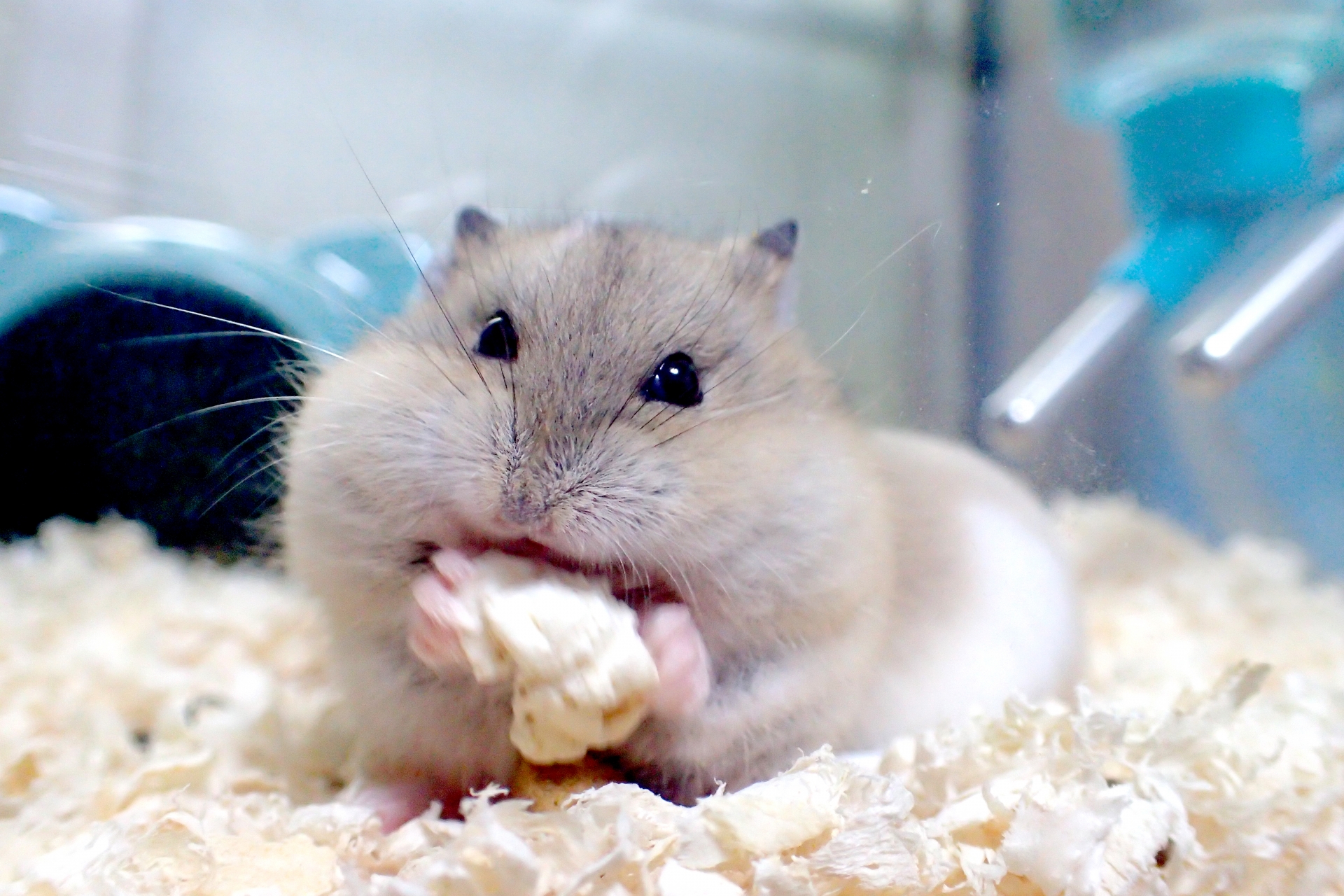寝かしつけの方法を知りたい!
新生児の頃は、ミルクや母乳を飲めば寝てくれたのに、生後3ヶ月にもなってくるとそう簡単には寝てくれなくなってきます。
また、ママの産後疲れや育児疲れも溜まってくる時期ですから、しっかりと寝て日々の子育てに備えていきたいところです。
ですが、赤ちゃんの寝付きが悪かったり、夜泣きがひどいとママもしっかりと眠れずに疲れが貯まるだけですよね?
赤ちゃんが眠たくなったら、自分の力で眠れるようにするために生後3ヶ月から、自力で寝られるようにしてみませんか?
生後3ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間や成長具合などを踏まえつつ、ママの睡眠もしっかりと確保できるような生活リズムを作っていきましょう!
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

身長171cmの標準体重は何kg?男性は見た目の体型にも注意
年齢を重ねていくと体重が気になる男性も増えていくでしょう。日本人の男性の平均身長は約171cmと言わ...
-

キャベツを変色で黄色くさせないコツや保存方法と切り方の秘訣とは
キャベツを長く保存しているとだんだん黄色く変色していきますよね。では、キャベツが黄色に変色す...
-

水道の蛇口掃除の簡単なコツや酷い汚れの対処法と清潔を保つ工夫
水道の蛇口の掃除はうっかり忘れていると蛇口が白くなってしまったり、黒くなってしまうことがあります。こ...
スポンサーリンク
【寝かしつけの方法】3ヶ月の赤ちゃんの成長具合と睡眠時間はどのくらい?
赤ちゃんの成長と睡眠時間
- 1日の平均睡眠時間は合計して13~17時間
- 体重は生まれてから約2倍くらいになる
- 首がすわってくる
- モロー反射が消えてくる
- 昼と夜の区別がつくようになる
- 空腹感や満腹感がわかってくる
生後3ヶ月の赤ちゃんの体重は、生まれたときの2倍くらいになり生後3ヶ月を過ぎると成長が緩やかになります。
原始反射であるモロー反射が少しずつ消えてくるのでビクッとすることが少なくなります。このため、寝かしつけが少し楽になることもあるでしょう。
首がすわってくるので、縦抱きが出来るようになります。だんだんしっかりしてくるのがわかりますが検診で首がすわっているかどうか確認してもらうといいでしょう。
首がすわり始めたころは、安定した抱っこのほうが赤ちゃんもお母さんも安心ですので状況や環境などによって今までのように横抱きで抱っこしてあげるといいでしょう。
まとめて寝る子もいれば、あまり寝ない子もいます。あまり寝ない子でも1日に13時間くらい寝ていれば大丈夫です。哺乳量が増えることから長く眠るようになります。睡眠の時間や回数は赤ちゃんによって違います。また、まとめて眠る時間が増えてくると起きている時間も増えてきます。
寝かしつけの方法がわからない!3ヶ月の赤ちゃんが寝なくなってしまう理由とは?
新生児期の赤ちゃんは授乳するか寝ているかといったように、眠る間隔が短くとも十分な睡眠をとっていました。
では、3ヶ月の赤ちゃんはどのような睡眠のリズムになるのでしょうか?
3ヶ月の赤ちゃんは、新生児の頃に比べて体力がついてきます。このため、起きている時間が多くなります。
生活リズムを整えることで、夜に眠る時間が長くなってきます。そうするためには静かすぎない環境にしてあげるといいでしょう。
今までは、眠りについた赤ちゃんを起こさないように静かな環境を作っていたかもしれませんが、昼の明るさや雑音が感じるように過ごしたり夜は暗く静かな環境を作るなどすると赤ちゃんは昼夜の区別をつけることができるようになってきます。
赤ちゃんは、授乳したりお風呂に入るだけで疲れますが昼間に光を浴びたり、雑音の中で過ごすことでも疲れます。少し疲れることで、夜長く眠ることに繋がるでしょう。
寝かしつけの方法。自力で寝られる赤ちゃんに。生後3ヶ月からチャレンジしてみよう!
今までは抱っこをして寝かしつけていたかもしれませんが、そろそろ添い寝で寝かしつけをしたいと思う生後3ヶ月頃。
どのようなことをすればいいのでしょうか?
おっぱいやミルクをあげ、ゲップをさせた後に布団やベッドに赤ちゃんを寝せます。
ママやパパは横で添い寝をしましょう。このときに側にいることがわかるように体のどこかを触ってあげると赤ちゃんは安心します。
「ママはちゃんと側にいるよ」と声に出すのもいいでしょう。赤ちゃんの呼吸に合わせて優しく背中やお腹をさすってあげましょう。頭を撫でたり、手を繋いだりしてもいいですね。
初めのうちは赤ちゃんを布団に置いたら泣かれてしまうこともあります。しかし、そのうちに慣れてくるのでお気に入りのぬいぐるみやタオルなどを使って安心させてあげましょう。
添い寝で寝かしつけをした場合、どのくらいで慣れるものなのでしょうか?
2週間以上かかってようやく慣れてくる赤ちゃんもいれば、数日で慣れてしまう赤ちゃんもいます。
赤ちゃんの寝かしつけをスムーズに行うためには朝の儀式が大切です!
赤ちゃんの寝かしつけをスムーズに行うためには、朝の行動が肝心です。
朝の8時頃に顔を拭いて、起こしましょう。温かいお湯につけて絞ったガーゼで顔を拭くことで、起きなくとも起きる準備ができるでしょう。
顔を拭いたら、カーテンを開け陽の光を浴びさせましょう。
子どもに陽の光を浴びさせることで、身体に一日の生活リズムを覚えさせることができます。
赤ちゃんが起きたら、すぐに抱っこをしたくなりますがいきなり抱きあげると赤ちゃんがびっくりしてしまうそうです。
びっくりして泣いてしまうこともあるので、起きてすぐはそっとしておきましょう。
毎回起きてすぐ抱くことで身体がびっくりして泣くことを繰り返していると、起きたときに泣いてしまう原因となってしまうので、オムツや汗をかいていないかなどをチェックしてから授乳をしてみましょう。
また、夜に眠る前の授乳量が少ないと深い眠りにつけません。ママが疲れる夕方から夜間にかけては授乳量が少ないこともあるのでママもしっかり休むように心がけましょう。
赤ちゃんは眠りが浅いってホント?
よく眠っている赤ちゃんですが、実は大人と比べて眠りが浅いんです。
大人は、深い眠りであるノンレム睡眠と、浅い眠りであるレム睡眠を90分周期で繰り返しているのに対して新生児は40~50分周期と短く、生後3ヶ月でやっと50~60分周期となります。
1歳半までは浅い眠りであるレム睡眠が全体の眠りの50%を占め、2歳になって大人と同じ20~25%までレム睡眠が減少するので、すぐに起きてしまったり、起きたと思ってもまた寝たりを繰り返します。
睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンですが、このメラトニン分泌のタイミングがずれていると夜に寝つきが悪くなってしまいます。
メラトニンは朝太陽の光を浴びてから14~16時間後に最も分泌されるので、この計算をして赤ちゃんを寝かしつけるといいでしょう。
朝7時に起こすと、21~23時に分泌のピークがきます。寝る30分前にはお風呂や着替えをすませ、部屋の明かりを暗くしてあげましょう。
朝の起きる時間がバラバラだと正しい時間にメラトニンが分泌されず、夜の寝つきに影響します。
夜の睡眠の質を上げるために、遊ぶ場所と寝る場所を区別してあげるのもいいですね。理想的な時間にちゃんと眠くなるようにするには、その前の3時間は寝かせないことを意識しながら、授乳やお風呂の時間を決めるといいでしょう。