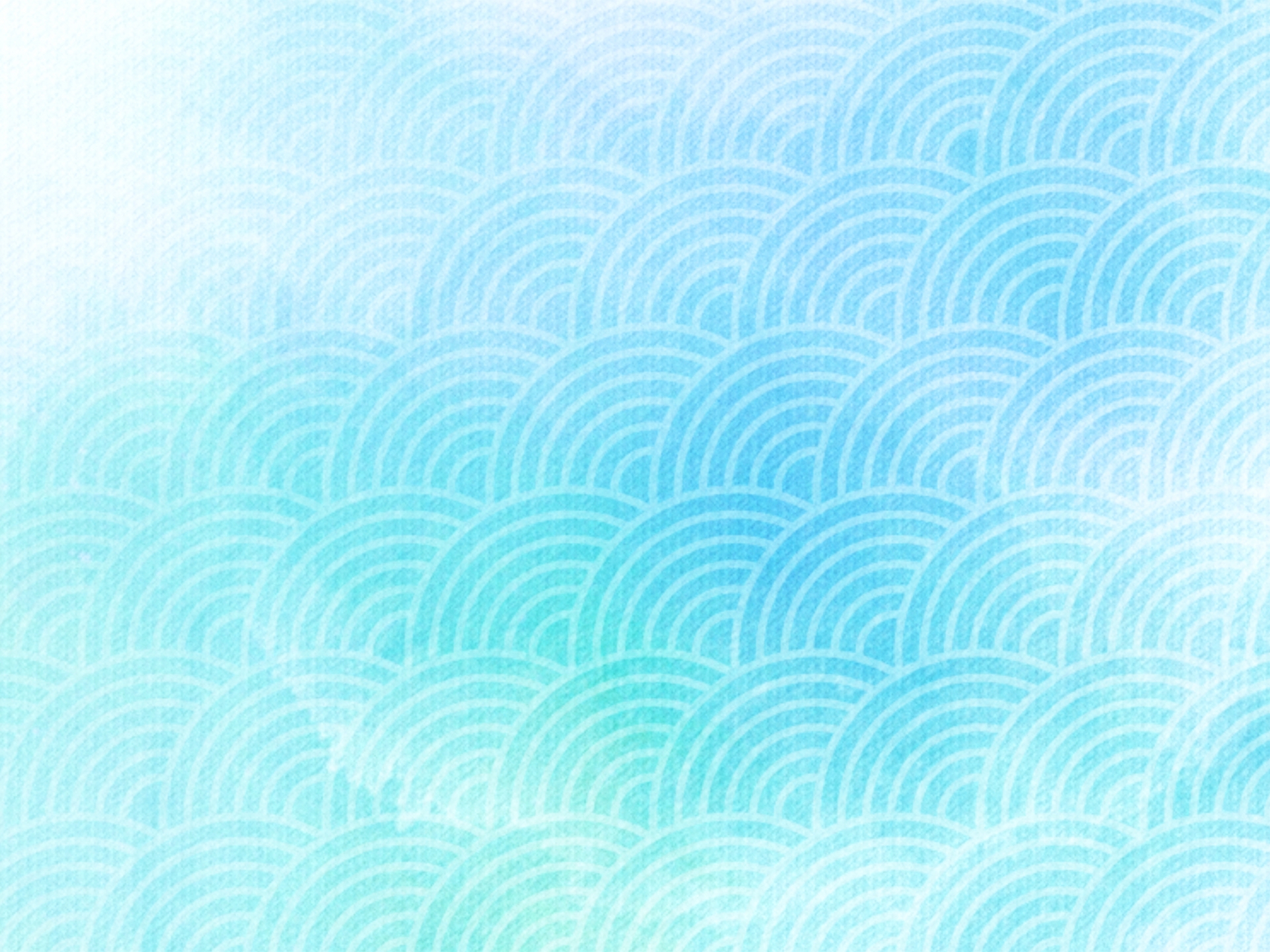水彩で背景を上手く描きたい!そんなあなたに、描き方のポイントについて詳しくご説明します。
水彩は段階に分けて塗ったり水の量を調整することで、背景をグラデーションやぼかしたりすることができます。
色の使い方やコツさえつかめば、素敵な背景を描くことがきっとできるはず。
練習をたくさんして、素敵な水彩画を作ってください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

体を柔らかくする方法【短期間】柔軟性を手に入れる極意を伝授!
体を柔らかくする方法。しかも短期間で!痛みに耐えてギュウギュウ可動域を広げても、柔軟性を手に...
-

メダカの底砂の掃除方法!掃除に便利なアイテムと水槽の掃除手順
メダカの水槽の掃除は欠かせないお世話のひとつです。掃除を怠ると水質の低下に繋がってしまいます。そ...
-

麺をすする方法は?上手に麺をすすれるようになる簡単な練習方法
日本にはラーメンやそば・うどんのように、麺をすすりながら食べる食べ物がたくさんあります。でも、中には...
-

セラミックのフライパンの手入れ方法!長持ちさせる使い方のコツ
セラミックのフライパンの手入れはポイントをおさえればどなたでも簡単です。セラミックのフライパンはフッ...
スポンサーリンク
水彩画で背景をグラデーションにしたい時の描き方
水彩画の魅力の1つは透明感のあるグラデーション表現です。
特に海や空などの背景で単一色のグラデーションをベースにすることがあると思います。
広い面のグラデーションをきれいに表現する描き方では、紙を先に濡らしておいてから描き始めます。水は紙にたっぷりと染み込ませてください。
そして紙全体に均一に馴染むまで少し待ってから色を塗り始めます。
この時、使う色は一色であってもあらかじめ適量に溶いた絵の具を多めに準備しておきましょう。
途中で色が足りなくなって絵の具を継ぎ足すと濃度に違いができ、色ムラの原因になります。
そして、色を含ませた筆で濃い部分から薄い部分に向かって塗っていきます。この時、必ずできるだけ一気に薄い方まで筆を勧めます。
そして薄い方から濃い方には筆を動かさないようにすることが重要。ためらって逆に筆を進めるとムラになります。
コツは慌てる必要はありませんが、落ち着いて一息で色を置くことです。
にじむような背景にしたい時の描き方のコツは、水彩紙にたっぷりの水を塗ること
隣り合う色が互いに混じりあって生まれる「にじみ」や、水を加えて色の「ぼかし」も水彩画の魅力的な味わいです。
紅葉の木々や一面に色とりどりの花が咲き誇る風景では、背景にも使える技法です。
逆に、1枚の葉のように1つのものを描く時に複数の色をにじみで表現すると、独特の深みが描けます。
この技法でもポイントは先に紙に水を含ませておくことです。
濡れた紙に色を置くと自然と色が周囲に広がっていきます。乾かないうちに先に置いた色の中や、少し離れた場所に別の色を置くと互いの色が自然ににじんで混じり合います。
思ったとおりの色を描くことは難しい技法ですが、偶然生まれるグラデーションは意外性があり楽しいものです。
また、水だけで絵を描くように一部分だけを濡らしておいて、濡れた部分に色を置くと乾いている紙へは色が広がらないので思った範囲だけでにじみやぼかしを表現することができます。
背景の描き方、水彩は水の量を上手く調整するのが一番のポイント
水彩画で描かれた風景画は、その透き通るような風景と紙の上とは思えない奥行きの妙があります。
背景を描く場合、奥に見えるものほど色は薄く見え、山々などは青みがかって見えるでしょう。
手前にあるものほど陰影がはっきり見えるので、奥、中間、手前で一番暗い部分の色が同じにならないように意識しましょう。
濃さを上手に調節するのは、やはり水の使い方です。薄くにじませる部分は水を多めにした色で、手前は水を調整してはっきりした色でメリハリを出しましょう。
水彩画では、始めに大まかなイメージを鉛筆で薄く描いていきますが、絵の具を使う時は線では無く面で色を置き、筆を進めていくと徐々に薄くなるグラデーションを活用して描く事が必要です。
また、雲のように白い部分や強く光が当たる部分は色を乗せず、画用紙の白を残して表現するのが一般的です。後から白で塗ることは水彩画ではあまり行いません。
水彩画は紙の上で色々な色を重ねる描き方ができるのも魅力の一つ
水彩画の魅力は透明感の表現だとご紹介してきましたが、透明であるがゆえにできることが「重ね塗り」による深みのある着彩です。
最初から2つ以上の色を混色するのではなく、紙の上に別々の色を重ね塗りすることで生まれる色はパレットの上で絵の具を混ぜた混色とは違う表情になります。
同じ色を使っても塗る順番が違えば異なる色になります。まず赤を塗ってから青を重ねるのと、青を塗ってから赤を重ねるのでは同じ色味にはなりません。
また、赤と黄色、青と黄色など濃く強い色と明るい色や薄い色を塗り重ねた場合、どうしても濃い色が勝ってしまうので塗る順番には気をつけましょう。
重ね塗りをする時の鉄則は「薄い色を先に塗る」ということを忘れないで下さい。そして強く光があたった表現や白を強調したい場所は、絵の具の白を使うのではなく紙の白さをそのまま生かして表現します。
あまり色数を重ね過ぎても色が濁ってしまうので、色々な色の絵の具で重ね塗りを試して自分好みの表現を探してみましょう。
水彩絵の具の透明水彩と不透明水彩、それぞれの特徴と使い方
透明水彩絵の具の特徴と描き方のポイント
透明水彩絵の具は、その名の通り色に透明感があり一度色を塗った上から別の色を塗ると塗りつぶされずに色が重なることです。
あらかじめパレットの上で絵の具を混色した場合とは違い微妙で味わいのある色になります。
ただし、重ね塗りを繰り返すと色が濁ったり暗くなるので注意しましょう。
不透明水彩絵の具の描き方のポイント
適度な水の量で塗ることで均一でムラのない色が濡れるのが不透明水彩絵の具です。一度塗った上に色を塗ると下の色を隠した描き方ができます。
マットな厚塗り表現も可能ではありますが、乾燥してからひび割れを起こすことがあるので適度な水の量を把握しましょう。
水の量を増やすと透明水彩に近い使い方もできますが、透明感では透明水彩絵の具には劣ります。
どちらも水に溶ける性質なので一緒に使うことは可能ですが、それぞれの特徴を上手に知って使い分けることが必要でしょう。
多くの人が小学校の授業で触れる絵の具は一般的に不透明水彩ですので、透明水彩との違いに慣れるまで戸惑うことがあるかもしれませんね。
でも、いろいろな技法を試して自分が描きたいものに必要な技術を身につけていきましょう。
難しく考えなくても楽しんで描いているうちに見についていくはずです。教室やサークルなどで先生に習ったり、仲間と楽しく描くのもいいですよ。
うまく描けるようになったら素敵な額縁を探して飾る楽しみもできますね。