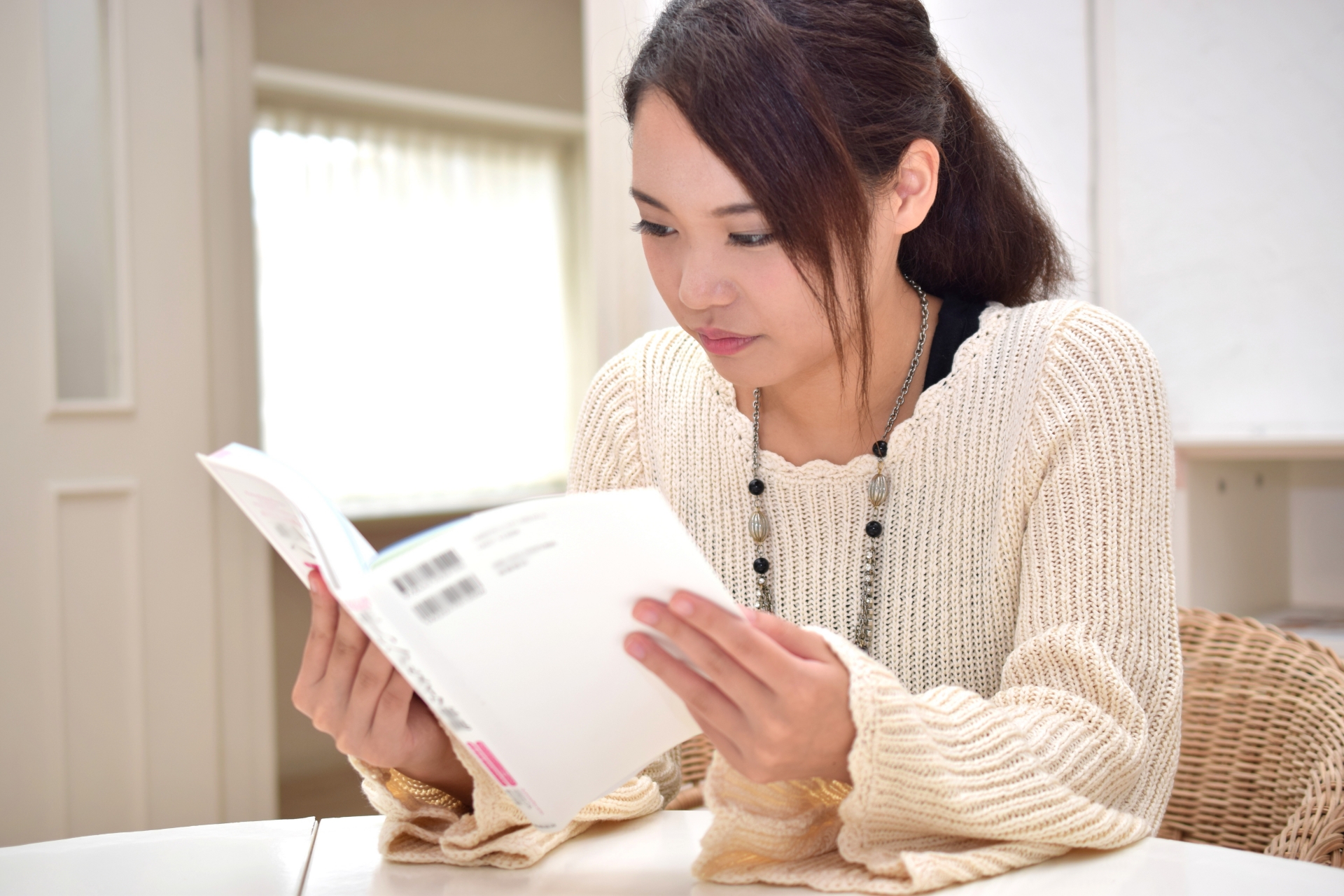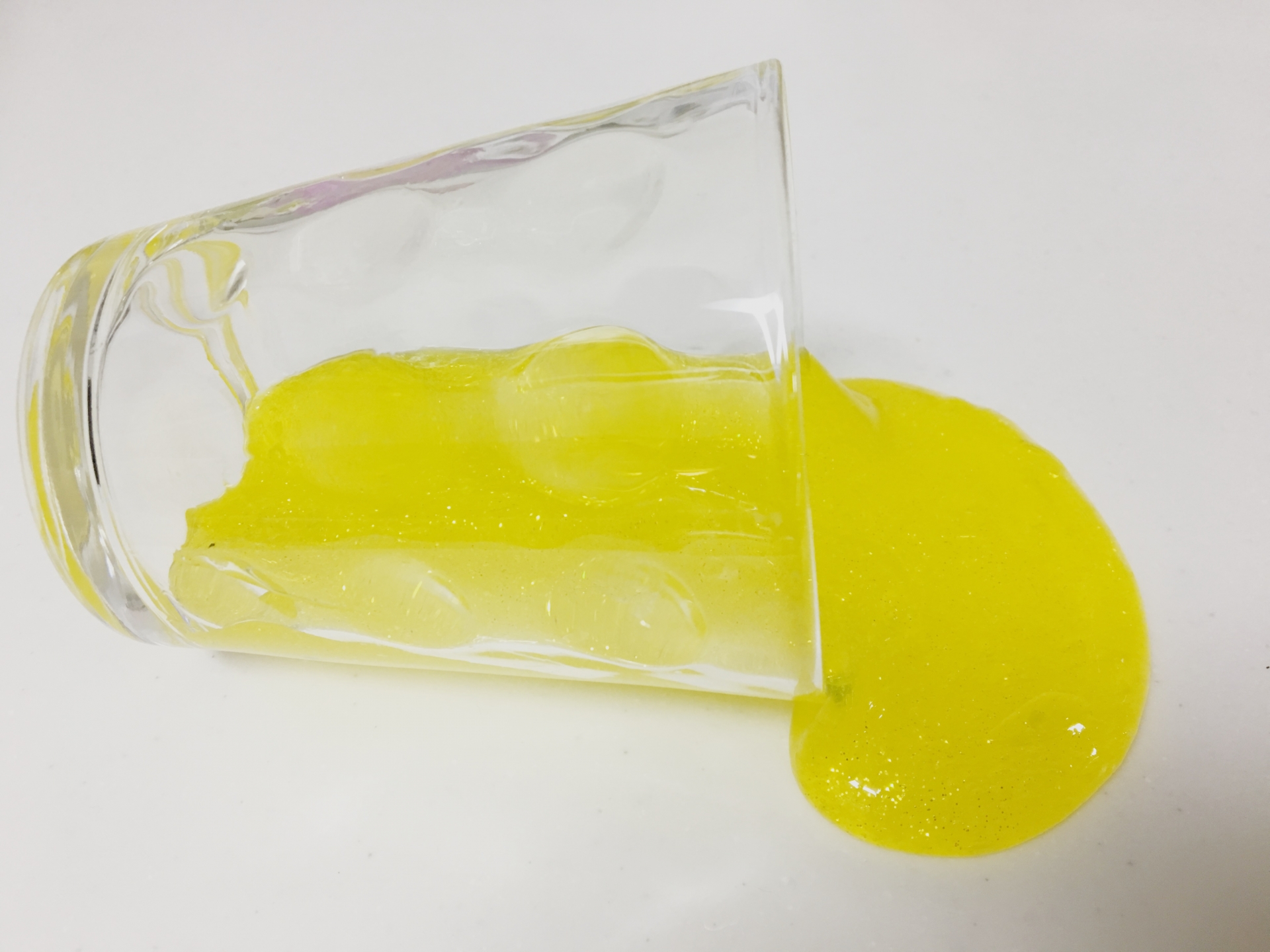子供の教科書の整理をしたいなら、100均グッツを上手く活用した整理方法がおすすめです。
すべて100均で揃えることができますし、子供も使いやすく出し入れしやすい収納アイデアが満載!
今すぐ真似したいアイデアばかりです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
教科書を整理する時に迷う、前学年で使用した教科書の整理や捨てるタイミングも併せてご覧ください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

スマホのWi-FiがONにならない時にあなたがやるべきこと!
家に帰ってきてスマホを使おうとしたらWi-FiがONにならない…。そんな時「もしかしてスマホが故障し...
-

トイレのコンセントの位置は失敗しないようにしっかり考えよう!
日本のトイレといえば温水洗浄便座が当たり前のようになってきていますが、使用するためにはコンセントが必...
-

定期預金の引き出しを本人以外が行うには?引き出し方法と注意点
定期預金の引き出しは原則として名義人本人しか行えません。ただ、親が認知症で手続きができない、ある...
-

ボールペンのインクの落とし方!服についたボールペンの落とし方
うっかりしてボールペンのインクを服につけてしまうこともあります。ペン先をしまわずにそのまま胸ポケット...
スポンサーリンク
教科書を整理!100均グッツを使った収納アイデア
子どもが使用する教科書は何冊もありますし、その大きさや厚みもバラバラです。
子どもが使いやすいように教科書を収納したいけれど、どうしたらいいか分からないと悩んでいる人は多いのでないでしょうか。
100均グッズをフル活用して整理整頓を
100均グッズを使用して、子どもが使いやすいように教科書を収納することが出来ます。
100均グッズにはさまざまな物が売られていますが、子どもが使いやすいように教科書を収納するのであれば、まずは書類スタンドを使った収納がおすすめです。
書類スタンドを使用して教科書を収納することによって、何冊もある教科書を収納して取り出したとしても教科書が倒れてくることがありません。
書類スタンドがあることによって子どもでも教科書を収納しやすく、そして取り出しやすい状態に出来るところがおすすめです。
100均であれば気軽に購入することが出来るので試しやすいところもおすすめです。
一度、お近くの100均で見てみてはいかがでしょうか。
すぐには捨てられない前学年の教科書も100均グッツで整理可能
学年が上がることによって、新しい教科書を使うようになります。
そのため前学年で使用していた教科書は、普段の学校の授業では使用することが無くなります。
古い教科書はとっておくべき
授業で使用することが無く、既に学び終えた内容なので前学年の教科書を捨ててしまうという人も多いでしょう。
しかし、既に学び終えた内容の教科書とは言え、人間は復習しなければ学習内容を忘れてしまいます。
そんなときに、復習するための教材が無ければ新たに購入しなければいけなかったり、子どもが分からないままにしておくといったことも出てくるかもしれません。
子どもが学び使い慣れた教科書を捨てずにとっておくことによって、復習したいときにすぐに復習できる環境を整えておくのは大切なことです。
そのため、前学年で使用した教科書は捨てずにとっておくのがおすすめです。
そして、そんなときにも活用できるのが100均グッツです。
前学年の教科書は、頻繁に使用するものではありません。
頻繁に使用しない教科書は、100均のフタつきダンボールに収納する
箱に「○年生教科書」と書いておけば箱の中身も一目瞭然です。
子どもも箱を見ればすぐに中身が分かるので、必要な教科書を取り出してすぐに復習することが出来ます。
教科書を整理する時は、100均グッツなどを使って小分けにすること
何冊もある子どもの教科書を、子どもが使いやすいように整理するにはポイントがあります。
教科書を収納しやすく取り出しやすい状態に整えてあげる
大人であればブックエンドを使用してするだけでも、本が収納しやすいと感じるでしょう。
しかし、子どもの場合にはブックエンドだけの収納だけでは物足りないと感じることがあります。
ブックエンドを使用していても、ブックエンドを倒してしまって教科書がなだれのように落ちてきたりすることもあり上手に使いこなせない場合があるのです。
そのため、ブックエンドよりもしっかりとしていて教科書を小分けして収納できるグッツがおすすめです
例をあげると、100均でも購入することが出来るファイルボックスもおすすめです。
ファイルボックスであれば底もしっかりとしており、ファイル自体に高さもあるので教科書がなだれのように落ちてくる心配がいりません。
子供が整理しやすくなる!どの教科書かがひと目でわかるおすすめアイデア
教科書やノート自体に工夫をすることによって、子どもが教科書を整理しやすくすることも出来ます。
教科書やノートにラベリングをする
教科書には教科名が書いてあるので、収納していたとしても比較的すぐに取り出したい教科の教科書を取り出すことが出来ます。
しかし、ノートの場合にはどうでしょうか。
取り出したい教科のノートを取り出すときには、ノートの表紙を見てからでなければ取り出すことが出来ないでしょう。
取り出したい教科のノートと教科書をすぐに取り出すためには、一目見てどの教科のノートと教科書であるのかが分かる状態にしてあげればいいのです。
そのために、教科書とノートにラベリングをしてあげましょう。
子どもでも分かりやすいラベリングの方法が、色によって教科を分けるという方法です。
例えば、赤色がついている教科書とノート、ワークは国語。
青色がついている教科書とノート、ワークは算数といった漢字です。
それぞれの教科で色を分けてあげることによって、子どもでも一目で見てすぐにどの教科の物か判断することが出来るようになります。
教科書を捨てるタイミングはいつなのか
前の学年で使っていた教科書やワークをとっておくことによって復習することが出来るので、前の学年で使っていた教科やワークをとっておくことは大切です。
しかし、子供が高校生になってまで小学生の教科書はとっておく必要があるでしょうか?
必要が無いと答える人がほとんどではないでしょうか。
高校生になったら小学生の頃に使っていた教科書が必要ないのか?
小学生の頃に学んだ内容を復習する必要がないためです。
ということは、復習する必要がなくなった教科書やワークというものはとっておく必要がないということなのです。
いつまでも使わない教科書やワークをとっておいてしまうと、家の中に収納しておく場所を減らしてしまうことになります。
そのため、子供の学年が変わるごとに、家の中に置いといてある教科書やワークが必要かどうか見直すようにしましょう。
見直す方法で一番簡単な方法は、子どもに尋ねてみること
子供が復習に使っている教科書はそのまま家の中においておき、復習に使っていないという教科書は捨ててしまうのです。
こうすることによって、子どもにとって必要な教科書やワークを残しておくことができますし、不要な教科書やワークは捨てて家の中をすっきりとすることができます。