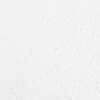絵の上手い人は下手な人と脳の使い方が違う?上手い人と下手な人にはどのような違いがあるのでしょうか?
絵は、描けば描くほど上達します。それは、いつもと違う脳の部分がよく働いているせいなのかもしれませんね。
絵が下手な人は、下手だからと描かない人で上手い人は上手くなるまで描き続けた人と言えるでしょう。絵が上手くなるためのコツを紹介します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

貯金額が300万円を目指せ!一人暮らし・低収入でも貯めるには
貯金額目標300万円!一人暮らしでも、低収入でもしっかりと貯金をする方法をお教えいたします!...
-

ファンヒーターに灯油が入れっぱなし!使えるかどうかの基準とは
寒くなってきてファンヒーターを使おうと出してみたら、去年使い切れなかった灯油が入れっぱなしになった、...
スポンサーリンク
絵の上手い人の脳はどうなっている?上手い人の描き方
同じ物を描いたはずなのに、一人はすごく上手くて、もう一人はすごく下手なんて事はよくありますよね。
同じ人間なのに、絵の上手い人の脳はどうなっているのでしょうか?
上手い人の描き方についていくつかご紹介します。
絵が上手い人全体のバランスを確認してから描く
例えば動物を描く時に、絵が苦手な人は頭や体など自分が描きやすい部分から描いていき、最終的に頭がやたらと大きくなったり、足がついている場所がおかしなことになったりしますよね。
それは、全体のバランスを確認せずに描いているからです。
上手な人は「顔に対して体の大きさはこれくらい」、「足と尻尾のついている場所はこうした方が自然になる」など、全体を見てから描き出し、描きながらも何度もバランスを調整しながら描いています。
物を記号的に捉えない
絵の上手い人のなかには、記号的なイラストで絵を描く人もいます。
しかし、それは目で見たものを一旦頭の中に置いて、それを理解してから絵に起こしているのです。
絵の下手な人は見た物を記号のように捉えています。
そのため顔のパーツを描く時も「目や鼻の形はコレ!」と自分で決めた形しか描けないので、動物を描く時も人間を描く時も同じような不気味な生き物で描くことがよくあります。
たくさん描いている
「たくさん描いてるのと脳は関係ないんじゃない?」と考える方もいると思いますが、たくさん描けるという事は、絵を描く事を苦痛に感じていないということです。
普通の人は何個か絵を描いたら疲れてしまいますし、それを毎日やれと言われたら、逃げ出してしまうでしょう。
しかし、絵の上手な人は率先して絵を描こうとするので、必然的に絵が上手になるのです。
絵の上手い人は記憶力がいい?脳の使い方
絵が上手い人のなかには、それが目の前になくても、かなり正確に描ける人もいます。
絵の上手い人は記憶力がいいのでしょうか?
その時、脳の使い方はこのようになっているようです。
絵が上手い人の全員が記憶力が良いわけではありません。
しかし、そのなかでも記憶力が良い人がいます。
そういった人は、見たものを出来るだけよく観察し、脳の中で記憶します。
そしてそれを紙に描き写す時にそれを再現するだけなので、周囲が驚くような正確さで描く事が出来るのです。
言葉で説明するのは簡単ですが、実際に行うのはとても難しいことです。
生まれ持っての能力か、相当な鍛錬を積んだ人にしか出来ないでしょう。
そうではない普通の絵の上手い人は、記憶力が無くても、模写力が高いので、見たものなら上手に描くことが出来るので、また違った能力だと言えます。
絵の上手い人は脳のここが発達しているのかも
絵の上手い人は脳のここが発達しているのかも知れません。
絵が上手い人は右脳が発達している
右脳が発達していると、得やすい能力は、「空間認識能力」や「立体把握能力」です。
空間認識能力は、物や自分がどのくらいの距離で離れているか、また位置関係などを把握する能力です。
そして立体認識能力は目の前の物を立体として把握する能力です。
ですので、テーブルの上の果物を描こうとした時に、その2つの能力が優れていれば、テーブルやお皿、それからいくつかの果物の位置関係や立体感をしっかり把握して、それを絵に書き出すことが出来るのです。
ただ、この2つの能力が優れているから=絵が上手いという風には必ずなるわけではありませんので、ご注意ください。
絵を描くのは、意外に複雑な能力なんですね。
絵の上手い人と下手な人の違いとは
絵の上手い人と下手な人の違いとはどういったものがあるのでしょうか。
そのいくつかを見てみましょう。
観察力
絵の上手い人は物をよく観察し、「ここはまっすぐに見えるけど、少し曲がってる部分がある」などを見つけてそれを絵にも再現します。
しかし、絵の下手な人は、あまり物を見ず全部真っ直ぐな線で描こうとしたり、小さく曲がって描けば良い部分も大げさに描いてしまいおかしな絵にしてしまいます。
筆圧
相当絵の上手い人では無い限り、一切に消しゴムなどを使わずに一度で絵を描くことは難しいことです。
それは絵の上手な人もわかっていますので、間違った線を描いてしまっても消しやすいように弱い筆圧で描くことが多いです。
しかし、絵の下手な人はあまりそういった事を考えないため、全力の筆圧で描き、間違って直す時も綺麗に消せずに汚い絵になったり、直さないで完成としてしまうことがあります。
視野
絵の上手い人は描きたい対処物だけではなく、自分の絵に対しても全体のバランスを見たり、細かいところを見たりなど、その時に合わせて視野を広げたり狭めたりしています。
絵の下手な人はそれが出来ないので、後先を考えずに描き始め、最終的にアンバランスな絵を描き上げてしまいます。
絵の上手い人は脳を喜ばせながら描いている?上手くなるヒント
「絵の上手い人は脳を喜ばせながら描いている?」
ここでは絵が上手くなるヒントについてご紹介します。
絵が下手な人は、自分の絵が下手な事を自覚できなかったり、自分の絵の下手さが嫌になって絵を描くのを拒否してしまう事があります。
それは、脳でも思考が遮断してしまうので、それ以上の向上が望めません。
しかし、絵の上手い人、または絵を描くのが好きな人は、自分が描いた絵の中で「ここの線が上手く描けた」、「ここの色が上手に塗れた」など、良いところを見つけられます。
また、その時は上手く描けなくても、「次は上手く描いてやる!」など意欲を燃やして次々と絵を書き続けていきます。
そのようにして、脳に適度な刺激を与えたり、達成することで喜びや幸福感を得るのです。
そういった小さな成功体験や、やる気の上昇が積み重なることで最初はあまり上手ではなかった人でも、数年後にはプロ顔負けの上達ぶりを見せることもあるのです。
絵の上手い人は、最初から脳が絵を描くことに向いているだけではなく、訓練によって上達するだってあるのです。
ですので、「好きこそ物の上手なれ」という言葉があるように、絵が好きで描き続ける気持ちさえあれば、どんな人でも絵は必ず上達します。
日々の努力を忘れないようにしましょう。