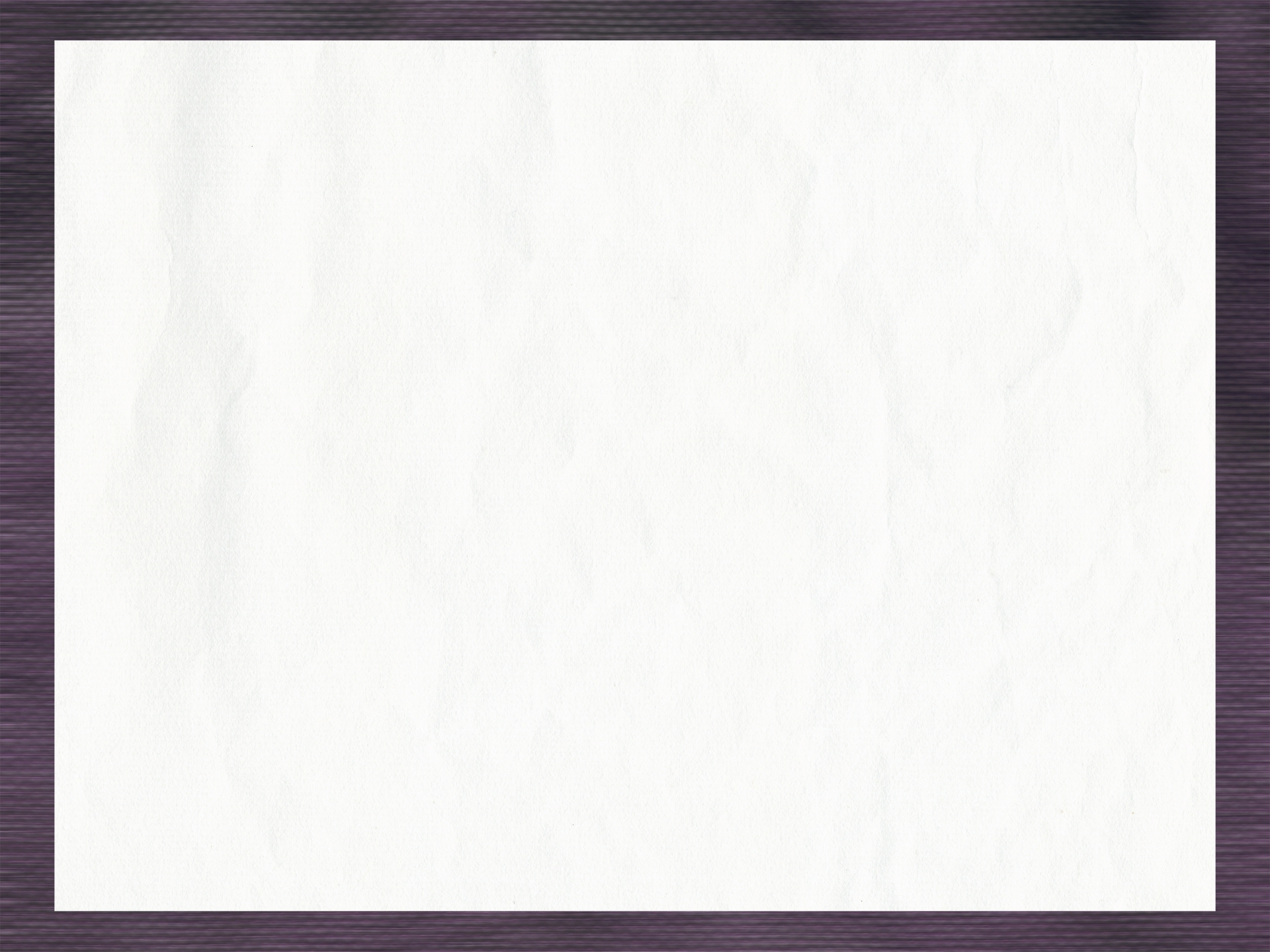習字の下敷きが汚れてしまったら、洗ってキレイにしたいと思いますよね。でも、どんなふうに洗うのが正しい洗い方かわからない人もいるでしょう。
習字の下敷きは普通にお洗濯をしても問題はないのでしょうか。洗濯してはいけない素材の下敷きはあるの?
そこで今回は、習字の下敷きが汚れてしまった時の洗い方と、下敷きの代わりになるものの選び方についてお伝えします。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

スノーボードウェアの上下同色はアリ?スノボウェアの着こなし術
スノーボードウェアはどのように選べばいいのでしょうか?ボードは初心者でもウェアはかっこよく、可愛く着...
-

日本の国技であるスポーツとは?まず国技の定義について考えよう
日本の国技ってどのスポーツなんだろう?って考えることってありますよね。相撲?それとも柔道?空...
-

朝ごはんはトースト&卵という人のためにアレンジ方法を教えます
仕事に行く前の時間がない時でも、朝ごはんはちゃんと食べたいですよね。でも、いつもトーストと卵...
-

おでんのこんにゃくの下ごしらえはおいしく食べるために必要です
冬になると恋しくなるおでん、コンビ二のおでんもおいしいですが、自分で好きな具を入れて作った方がよりお...
-

香水は古いけど使い道によってはオシャレに再利用できちゃいます
古い香水ってなかなか使わなくなってしまいますが、そんな古くなった香水でも使い道があるんです!...
-
No Image
かわいいノースリーブを見つけたけど、太い二の腕が気になって購入をためらってしまうという経験はありませ...
-

キャベツを変色で黄色くさせないコツや保存方法と切り方の秘訣とは
キャベツを長く保存しているとだんだん黄色く変色していきますよね。では、キャベツが黄色に変色す...
スポンサーリンク
習字の下敷きの洗い方・洗濯をしても大丈夫?
質問
小学生の子供が習字を習い始めました。
筆は使うたびに洗っていますが、下敷きは洗濯をしてもいいもなのかわかりません。
洗濯OKな下敷きとNGな下敷きはありますか?
回答
洗うと波のようなシワが付いたり、ゴワゴワになったり、部分的に伸びたりしてしまうので、フェルトでできた下敷きは洗わない方が良いでしょう。
ラシャ製の下敷きなら軽く洗う分には良いですが、干す時伸ばし伸ばしで干さないと微妙に縮みます。
部分的についた汚れだけを水洗いする程度であれば、どちらも可能のように思えます。
ただし、変な形に伸びたりシワが付いた場合、アイロンをかけても治らないこともあるので、注意が必要です。
習字の下敷きの洗い方は種類で違う!手洗いできない下敷きもあります
習字に使う半紙はとても薄く、水分をよく吸収するため、下に何も敷かずに文字を書くと吸収しきれなあった墨で机や床を汚してしまいます。
それを防ぐために使用するのが下敷きです。
下敷きは必ず揃えなければならないものではありませんが、机を汚さないためにもできれば使用したいものです。
下敷きの扱いを雑にしていると、シワがついてしまうこともあります。
シワがあると、文字を書いているときに筆が引っかかってしまい作品をダメにしてしまうこともあるため、できるだけ丁寧に扱うようことが大切です。
では下書きの種類を見ていきましょう。
習字用の下書きには主に、 ラシャ製とフェルト製の2種類があります。
それぞれの特徴については後ほど詳しく解説します。
下敷きには基本的に裏表はありませんが、中には片面に滑り止めの加工がしてあるものや、紙の中心に線が引かれたものや、文字を書く目安に罫線や四角い枠がプリントされたものもあります。
また、下敷には様々な色があり、一般的な黒や紺は墨の汚れが目立ちにくく、白は半紙に透けて下敷の色が見えないので、作品を作る際にイメージを邪魔しないというメリットがあります。
習字の下敷きの特徴と洗い方について
習字の下敷きは素材によって特徴が違います。
ここでは素材別の特徴をご紹介します。
高級感とボリューム感のあるフェルト製の習字の下敷きの特徴と洗い方
フェルト製下敷の素材は「合成繊維+ウール」です。
毛を圧縮して作られていますので、高級感やボリューム感があります。
後述するラシャ製よりも高価ですが、先ほど触れた色の種類も多く好んで使用される方が多い下敷です。
感触は柔らかいのですが、シワが付きやすいので折りたたまずに丸めて収納したほうが安心です。
洗濯は避けてください。
シワになりにくい丈夫なラシャ製の下敷きの特徴と洗い方
素材は「ナイロン混+ウール」です。
毛を織り交ぜて作っているため伸び縮みしにくく、耐久性があります。
フェルト下敷に比べるとやや硬めの感触で、シワになりにくいのが特徴です。
そのため折りたたんで収納することも可能です。色のバリエーションは少ないもののフェルト製のものより安い点も特徴です。簡単な浸し洗い程度であれば可能です。
下敷きに種類があることをご存じなかった方も多いかもしれません。特徴を見るとわが子が使っているものはフェルト製なのだと今更気づきました。
習字の下敷きを選ぶ時のポイント
下敷きを選ぶ時のポイントはズバリ厚さです。
下敷きの厚さは1~3ミリのものが多いですが、収納時に折り目がつきやすいのでおすすめは2ミリ以上のものになります。
色は意外と種類があることは先ほども書きましたが、黒や紺などの濃い色を選べば、汚れは気にならないでしょう。
素材はラシャ製、フェルト製のどちらか好みで選びましょう。
罫線入りの下敷きは、初心者が文字をバランスよく書くにはとても便利です。
罫線入り下敷きを使えば、半紙の上からでもうっすら罫線が見えるため、安心感があるでしょう。
習字に慣れてきたら、逆に罫線にとらわれることがデメリットになりますが、初心者さんにはおすすめと言えます。
習字の下敷きの代わりになるものは?
先ほども書きましたが、習字の下敷きは必ず揃えなければならないものではありません。
ここでは下敷きの代用として使えるものをご紹介します。
手芸用のフェルト
書道セットは今でも決して安いものだとは言えませんが、昔は今よりももっと高価だったため、使い古した着物を下敷き代わりに使っていたこともあるそうです。
ちなみに手芸店などで取り扱っている、厚手のフェルトも下敷き代わりに使うことは可能です。その際はやや厚みのあるフェルトの方が書きやすいでしょう。汚れを気にしなければ、好きな色のフェルトを選べます。
新聞紙
我が家でも大きな作品を書くときには新聞紙を敷いています。
書き初めなど、年1回の作品のために専用の下敷きを買うのはもったいない気もしますよね。そんな時は新聞紙の出番です。1枚では薄くてすぐに染みてしまい、フローリングを汚してしまう可能性があります。新聞紙は少なくても3~4枚は重ねて使用しましょう。